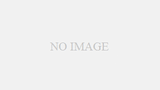焼き鳥屋を開業したい──
そう考えたとき、多くの方が「まずは修行だ」と思うのではないでしょうか?
ですが、5人に1人は**“自己満足の修行”**で時間もお金も失い、開業までたどり着けません。
このページでは、実際によくある失敗例と、「修行に失敗しないための視点」をご紹介します。
この記事の目次
なぜ「修行=正解」とは限らないのか?
飲食店開業でよく聞くのが「まずは修行してから」という言葉。
修行=成功、ではありません。
実際に以下のような“落とし穴”に陥ってしまう人が非常に多いのです:
– 憧れだけで修行先を選んでしまう
– 教わる内容が現場特化すぎて開業には不向き
– 数年働いても利益構造を理解できない
– 結果、開業前にモチベーションが尽きてしまう
特に「個人経営の居酒屋」で修行する方に多く見られます。
こうしたケースがあとを絶ちません。
なぜ「修行=正解」とは限らないのか?
5人に1人がハマる「修行の落とし穴」
✔️ 修行先を「雰囲気」だけで選んでしまう
✔️ 教わる内容が属人的で、他では通用しない
✔️ 雇われ側としての姿勢から抜け出せない
✔️ 「開業に必要な準備」がまったく分からない
👉 **このような状態で“とりあえず独立”しても、続かないのが現実です。**
失敗を防ぐために必要な“3つの視点”
① 修行先の「卒業生」が実際に開業しているか?
② 教える側が“再現性ある方法”を教えてくれるか?
③ 開業後まで支援があるか?
これらの視点で修行先を選ぶだけで、開業成功率は大きく変わります。
修行に頼らず開業する方法もある?
最近では、**“開業前提”で技術・ノウハウ・物件探し・収支計画まで一気通貫でサポート**
する仕組みも増えています。
「修行ではなく、開業から逆算する考え方」を知っておくことが、遠回りを防ぐ鍵です。
【LINEにて無料オンライン相談 受付中】ここから入れます。
「法人新規事業・独立・修行、このままで大丈夫?」
あなたの現状をヒアリングししてアドバイスをします。
なんとなく修行しよう」「有名店だから大丈夫」
そんな思い込みで、貴重な時間をムダにしてしまう人も少なくありません。
下記の実践的なことは教わるところを決めてから学び始める
焼き鳥屋の成功は、使用する食材の質に大きく左右されます。単に「美味しい鶏肉を仕入れる」だけではなく、以下のような要素を考慮しながら仕入れルートを確保する必要があります。
- どのブランド鶏を使うか? 例えば、地鶏なら宮崎地鶏、比内地鶏など。
- 地方ならではの強みを活かせるか? 地域特産の食材との相性を考慮。
- 一本あたりの重量と原価設定 例えば、40gと60gでは収益モデルが大きく変わる。
この実情を認識せず、店作りに金をかける機会損失
多くの人は、「店のデザイン」や「ユニフォーム」 などの表面的な要素に時間と資金をかけてしまいます。しかし、焼き鳥屋の成功は、味とオペレーションの効率化 によるところが大きい。店舗を作ることに意識がいきすぎて、最も重要な 「味」「サービス」「運営の効率」 を見落としてしまうケースが多いのです。
開業準備に必要な期間の設定
当初は半年程度で開業できると考えていたが、実際には1年以上の準備期間が必要だった という成功者の声が多い。
- 修行を通じて、技術を確立する期間
- 市場調査や物件選びの時間を確保
- 開業資金を安定させるための資金調達計画を整える
短期間での開業はリスクが高い。最低でも1年の準備期間を見積もるべきです。
修行における誤解と常識
なぜ常連になるための課題に立ち向かわないのか
多くの修行者が、「とにかく技術を磨けば繁盛する」 と思い込みがちです。しかし、これは大きな誤解です。繁盛する焼き鳥屋は、味だけでなく「店舗の運営力」「サービスの質」「マーケティング」 まで考え抜いています。
- 技術だけではなく、客の心理を理解することが重要。
- リピーターを増やす接客や店舗運営のノウハウを学ぶべき。
- 「売れる仕組み」を設計しないと、生存率が低くなる。
修行は、単なる調理技術の習得だけではなく、「売れる仕組み」を確立することに焦点を置くべきです。
焼き鳥屋開業の成功のカギとは?
成功する人の特徴
✅ 市場調査を徹底し、ターゲットを明確にする。 ✅ 技術を磨くだけでなく、運営の最適化にも力を入れる。 ✅ リピーターを増やす仕組みを設計し、長期的な繁盛を目指す。
失敗する人の特徴
❌ 内装にこだわりすぎて、運営の基本を見落とす。 ❌ 独学だけで学び、現場での実践を軽視する。 ❌ ターゲットを広げすぎて、誰にも刺さらない店を作ってしまう。
🔥 まとめ
焼き鳥屋開業で成功するには、以下の3つの視点を常に意識することが重要です。
- 技術の習得だけでなく、運営ノウハウを確立すること。
- 食材や設備の選定を戦略的に行い、長期的な視点で計画を立てること。
- お客様目線での体験を最優先に考え、リピーターを増やす施策を行うこと。